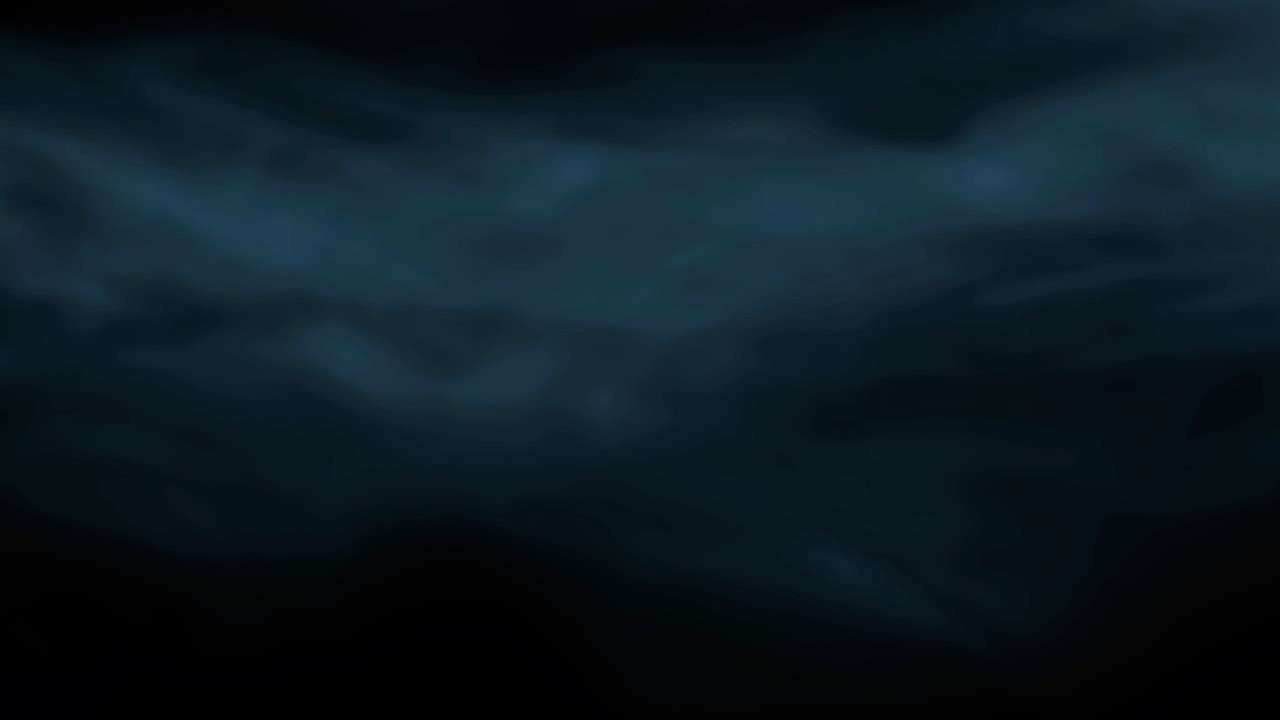はそのお金を貯金してくれた。その貯金通帳の口座名が、
《黒木俊雄の美術館をつくる会》
となっていた。
そのとき母はしみじみとした口調で言った。
「毎日の生活がきりきりまいでそんな余裕がなかったけど、よっちゃんのおかげでとても現実的になったわね。なんだかほんとうにできるように思えてきたわ」
すると妹までも、
「あたしもお姉ちゃんみたいに中学生になったらバイトするから」
「そうね。東京じゃとても無理だけど、どこか小さな村の森のなかならば土地だって買えるし。この通帳、私たちの希望ね。ありがとう、よっちゃん」
そうなのだ。それは私たち一家の勇気なのだ。
私の父は無名のままに倒れた画家だった。わずか三十八歳の命だった。その早すぎる死が、父にとってどんなにくやしく無念だったかということが、いまでも鮮やかに思い出すことがある。
イエロー・ブリック・ロード
その埠頭には赤煉瓦の倉庫が四つ五つと建っていて、その倉庫棟の前を通る道路もまた煉瓦が敷きつめられていた。高層ビルディングが次々と立っていくなか、そのあたりは古い時代の古い時間がたちこめているようだった。煉瓦通りを抜けると広場にでる。その広場の奥には全身をガラス張りにしたレストランが建っていた。建物の半分を海にのせていて、そのテラスから海に向かって長い桟橋を突き出している。その桟橋には白や青や黄色や赤にペイントされた幾隻ものクルーザーが停泊していた。そのあたりは煉瓦通りとはちがったなにか近未来といった景色が広がっていた。
そのレストランの前の広場は、都会の穴場というか忘れられた三角地帯というか、いつも空いているのでぼくたちが野球をするときは、
「イエブリにいこう」
「うん、イエブリだ」
と言って自転車をとばしていくのだ。イエブリとぼくたちがその広場を呼ぶのは、そのレストランの名が《イエロー・ブリック・ロード》で、それをちょん切ってつなげたわけで、それはぼくたちを解放させる、ぼくたちだけにしか通用しない、なかなかクールな呼び方だと思っているのだ。とにかく馬鹿ママたちが、学習塾とか、水泳クラブとか、ピアノとか、英会話塾とか、あっちこっち入れるもんだから、ぼくたちの毎日は忙しい。だからそんなものを蹴飛ばして、みんなそろってイエブリにいくときは心が燃え立つのだ。
そしてそれはぼくだけのことかもしれなかったが、ちょっと体があつくなる。というのはイエブリにいく途中、不思議なことにいつもシェパードをつれた外人の女の子と会うのだ。すごくかわいい子で、ぼくたちとすれちがうとき、その子は春のような笑顔でハーイと声をかけてくる。雄太とか、健治とか、守とかはその子に出会うと、ハローとか、ジスイズペンとか、ジスイズガイジンとか言っていたが、そのうちジスイズオマンコとかジスイズキンタマとか言って下品にガバガバガビガビ笑うので、ぼくはとてもはずかしかった。もしその子が日本語をわかっていたらなんて思うだろうって。そんな気持ちでちらりとその子をみる。するとその子はバラのような笑顔をぼくに、もっとここを強調すると、ぼくだけに送ってくるのだ。
その日もまた野球をやろうというみんなの気持ちが燃え立って、学習塾とか、水泳クラブとか、そろばんとかをそれぞれ蹴飛ばしてイエブリにいくことになった。ところがぼくは宿題を忘れ、その罰で掃除当番にさせられ、下校するのがみんなより遅くなってしまった。そんなことに時間を潰されたことが悔しくて、その時間をとり戻そうと全力疾走で家に帰ると、ランドセルをベッドに叩きつけ、グロ