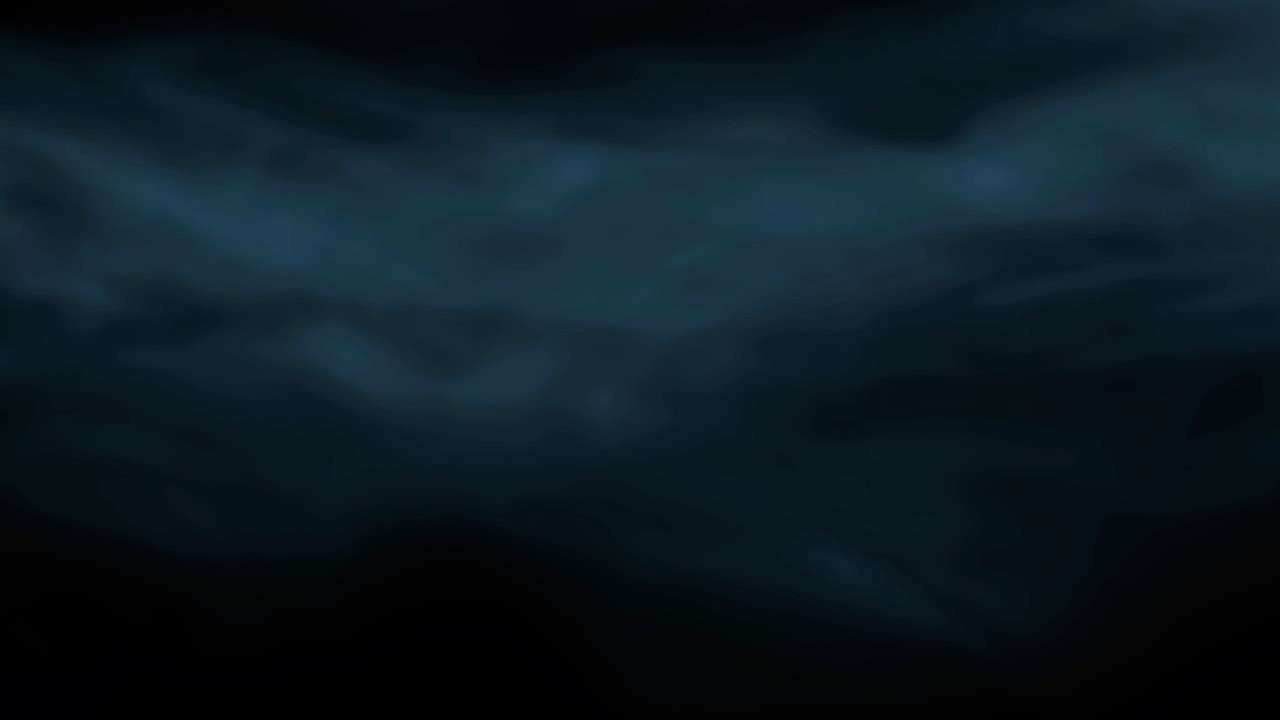の船は風まかせ
あんたが暴れた海は、
おいらの女房よりたち悪い
ああ、退散だ、退散だ
そしたらだ、そしたらだよ。起こったんだ、とんでもねえことが起こったんだ。海は依然として荒れ狂ってくる。風もさらに激しくなった。もうヨットはきりきりと悲鳴を上げている。万力になれとばかりに握りしめている舵は、ハンスをはじき飛ばさんばかりだ。しかし、そのとき、ヨットがふわりと浮いたんだ。巨大な波にもちあげられたんだ。ああ、もう終りだ。次にどっと海の上に叩きつけられる。ハンスの人生も終りだと思ったものだ。しかしなんということだ。ヨットは叩きつけられるどころか、ぐんぐんと空に舞い上がりはじめたじゃないか。空を飛んでいるんだ。ヨットが空を飛んでいるんだ。一杯に張った帆は、風をとらえぐんぐんと空に舞い上がっていくんだ。ハンスは何度も思ったさ。これが死ぬということか。人間はこうして天国にのぼっていくのかって。しかしこれは夢ではない。天国にのぼっているのでもない。たしかにハンスのヨットは空を飛んでいるんだ。海面がどんどん離れていく。さかまく波が、うねる波がだんだん遠くなっていく。ヨットは風をうけてどんどん高度をあげていくのだ。雲が走っている。その雲のなかにヨットは突っ込んでいく。一瞬あたりが真っ白になった。そこを突き抜けたとき、真っ青な空が見えたんだ。下をみると大海原だ。なんとヨットは空を走っているんだ。
青い海、青い島
父と私の二人だけの食事。いままでそれはもう賑やかな食事風景だったので、このはげしい落差は最初のうちはとても寂しかった。でもいまではこういう落ち着いた食事もいいものだと思うのだ。父はちょっと静かな人でいつも新聞を開いている。父が無口なぶん、私がおしゃべりだったから、なかなかいいバランスがたもたれているのかもしれなかった。
私は父になんでも話す。もう話しだしたらちょっと止まらないばかりなのだ。そんな私の話を父はビールをすすりながら開いた新聞の向こうで聞いている。
「ねえ、お父さん、今日ね、理科の先生があの人の話をしたよ」
「あの人って」
と父は広げた新聞の向こう側から言った。
「芦沢奈津子さんの」
「ふうむ、それで、どんな話をしたんだ」
「すごくほめるのよ、あの人は熱帯雨林を守った人だとか、破壊されていく自然を今でも第一線で守っている人だとか、鈴木先生はすごくその人のことをほめるけど、私はちょっと違うんじゃないって思ったわけ」
「どう違うんだい」
「つまり芹沢さんは、セブ島とかいう所にいくために家庭を捨てたわけでしょう、鈴木先生は捨てたと言ったよ、愛する人を捨て、生まれたばかりの子供を捨てたって、その捨てたという言い方にもすごくひっかかったけど、一番ひっかかるのはその人の生き方なのよ、その人がセブ島にいって、消えていく熱帯雨林を守るというならば、どうして結婚なんかしたわけ、どうして子供なんかつくったわけ、家庭を捨てていくならもともと結婚なんかしなければよかったでしょう、生物学者として地球を救いたかったら、結婚なんかしなければよかったのよ、だけどその人は結婚してしまった、そしたらその人が一番忠誠を誓わなければならないのは結婚した人にでしょう、二人の間に生まれた子供にでしょう、そうじゃない、お父さん、一つの家庭を守れない人にどうして地球が守れるわけ、私はそう思ってしまうのよ」
私のちょっと熱い口調に、父は新聞をおき、びっくりしたように私をみつめていた。そんな父に私は言った。
「お父さんは、このことをどう思うわけ?」
父はち