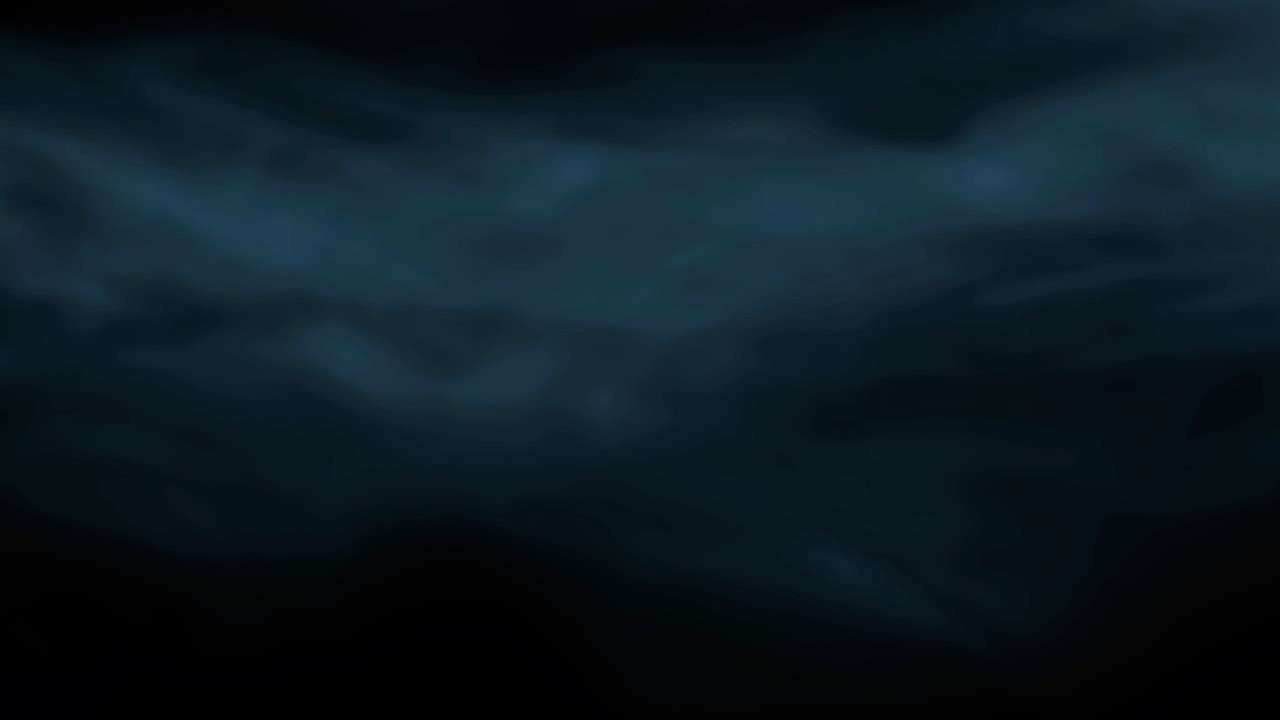うに走っていた。樫山もまた手を大きく振りながら走っている。突堤の先端にたどり着いた彼らは、ちぎれんばかりに手を振り、声を限りに叫んでいた。私もまた彼らの姿が見えなくなるまで手を振った。
この日、黒い雲が島を重く覆っていた。なにやらその景色は樫山たちの前方に横たわっている重々しい苦悩のようにみえた。そしてそれはまた私の前方に横たわる雲であるかもしれなかった。
豆腐屋
野口辰雄は四時に目が覚める。その時間は正確であって、柱にかかっている振り子時計が四時を告げる直前に、布団の上で半身を起こしているのだ。するとなんだか彼の起床にうながされてしかたなく振り子時計が、ボン、ボン、ボン、ボンと鐘を叩くかのようだった。商店会の寄り合いや、同業者の会合などがあって床に就くのが深夜になっても、彼が目覚めるのは四時だった。一日として四時の鐘を叩く振り子時計に遅れをとったことはなかった。五十年続けてきたその習慣が、彼の肉体の中に目覚まし時計のような正確な時刻を刻みこんだのだろう。
床から起き上がると、彼らが土間と呼んでいる作業場におりる。十畳ほどの空間に、水槽やコンロや炊飯竈が行儀よく並んでいる。四十年続けた作業である。手順は毎日きまっている。その作業を辰雄が行い、則子は彼の仕事を手伝う。野口豆腐屋の豆腐はそういう体制で出来るものだと辰雄は思っていた。しかし七年前、辰雄が交通事故にあった。豆腐や揚げ物を荷台のボックスに入れて行商するのだが、その行商中に車と接触してしまったのだ。交差する裏通りでの軽い接触事故だったが、しかしどっと道路に投げだされた辰雄は右腕を骨折してしまった。しかし野口豆腐屋は一日として休むことはなかった。則子がたった一人で豆腐を作りつづけたのだ。だれよりも辰雄はそのことに驚いたものだ。
七時には店のシャッターを上げて、ポリエチレンのボトルに入れた温かい豆乳を並べる。この暖かい豆乳を求めて、足を運んでくる客がいるのだ。近隣に住んでいる何十年来のお得意さんたちだった。このお得意さんたちも歳をとり、六十、七十になってしまった。毎朝、シャッターを上げると同時にやってくる吉江ばあさんはもう八十五歳である。キャリァカーで体を支え、弱った足を引きずるようにやってくる。しかし声は元気だ。そしていつも陽気だった。
「はあい、ババアは元気だよ」
「そうよ、おばあさん、いつだって元気印よ」と則子が応じる。
「あんたのところの豆乳に、元気だよって書いておきなさいよ」
「ついでに、くたばらねえ豆乳だよってか」
と奥から辰雄が茶々を入れた。
「そうよ、八十五までくたばらないってさ。ここにちゃんとした見本がいるんだから。あんたね、それって誇大広告じゃないよ」
「広告にするんだったら、九十ってところだな。九十歳までくたばらない豆乳だってさ。だから、あと五年はがんばってもらわなきゃあ」
「あんた、あと五年であたしをくたばらせるわけかい、冗談じゃないよ、あたしは、百歳までくたばらないよ、百歳まで生きてやるんだからね、あんたのところもがんばって、店をたたむなんて考えないでよ、なんでも、ニューヨークじゃ豆腐がはやってんだって、テレビでやってたけど、ダイエットすると動物性たんぱく質がすごく不足するから、ダイエットって野菜とかそんなものを食べて、肉を取らないだろう、肉を食べなくなると、動物性タンパツク質がへって、それが体にいろいろと悪影響がでるから、それで豆腐を食べるらしいのよ、それがさ、あんた、あっちの人のやることは大胆というか、気持ち悪いっていうかさ、豆