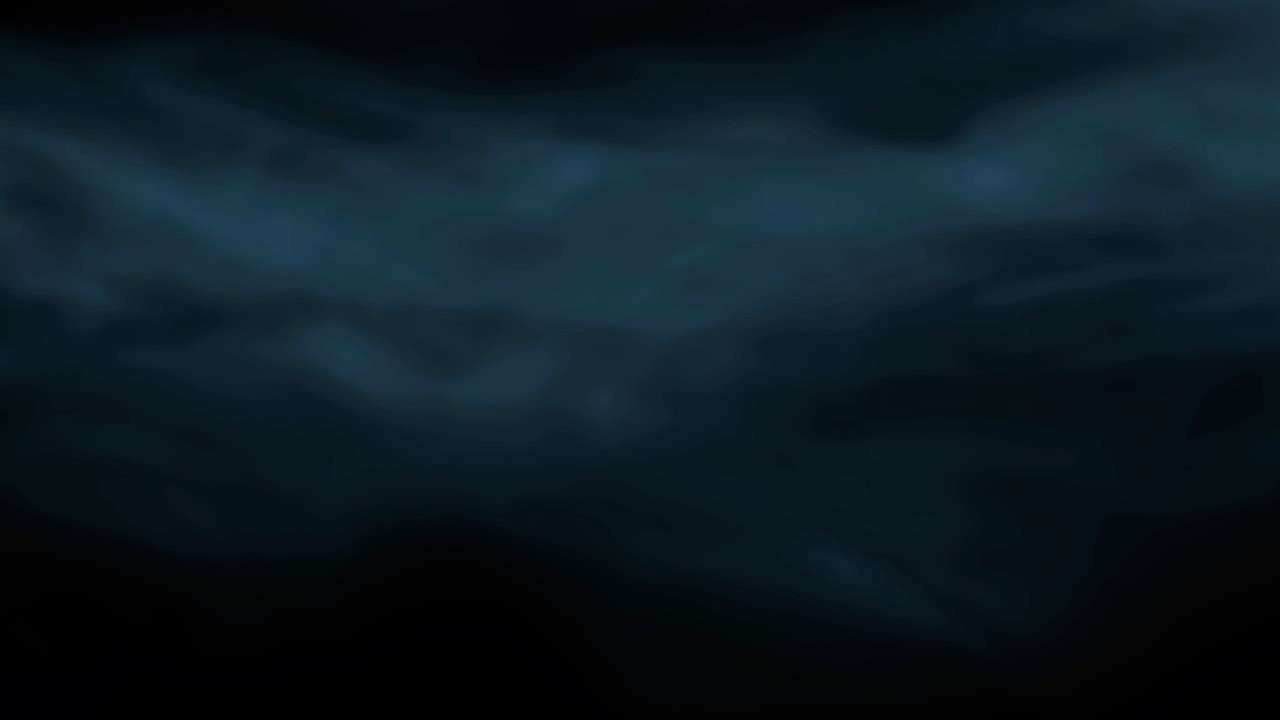ょっと呆然としたような視線を宙にはわせていたが、やがてなにかを決心するかのようにばさりと新聞をたたむと、ちょっと待ってくれと言って立ち上がり、食堂から出ていってしまった。なかなか戻ってこないので、どうしたのだろうと思っていると、父はミカンのダンボール箱を両手にかかえて戻ってきたのだ。そしてその箱をテーブルにおくと、私に言った。
「これはお母さんからきた手紙なんだ、お母さんの手紙がこのなかに全部入っている、こんなものをいままで大事にとっておいたのは、もちろんぼくのためである、過去にこだわるのはよくないことだけど、円(まどか)が生まれたときのぼくたちの歴史がいっぱいこのなかに詰まっているからね、この歴史はたしかにぼくたちのものだったんだ」
ふだん父は、私の前でぼくなどという言い方はしなかった。なんだかその言い方がとても新鮮だった。それはきっと青春の思い出が、父を青年のように若くしたからかもしれなかった。父は言った。
「しかしお母さんの手紙を、こうして大事にとってきたのはもう一つの理由があった、それはいつかそのときがきたら、円にこの手紙を読んでもらおうと思っていたのだ、どうやらそのときがきたようだね、お母さんはいっぱいお父さんに手紙を書いてくれた、これを全部読むのは大変だけど、でもきちんと読んでくれるね」
南の海の島 高尾五郎
南の海の島
豆腐屋
靴屋
私が友保坂嘉内、私を棄てるな
南の海の島
その遠く隔てた距離のために、卒業してからたしか二年目か三年目に一度東京で会ったきりだった。しかし年賀状とか、あるいはちょっとした近況のやりとりは続けていたのだ。ところが三年前、ひどく謎めいた、なにかただならぬ手紙をよこしたあと、ぷつりと音信を断ってしまった。それは私とだけではなく、彼と親しくしていた共通の友人にたずねても同様な返事がかえってきたから、私たちの前から姿を消さなければならない、なにかただならぬ事件といったものが、彼の身の上に起こったのかもしれないと思ったりした。
実際、その手紙は謎めいていた。分校をつぶしたとか、子供を殺してしまったとか、一家を虐殺したとか、村をつぶしたとか、ぼくは裏切り者だとか、この罪を永遠に許さないといった言葉が書かれていたのだ。しかしそれ以上のことはなにも書かれていない。いったい村をつぶしたとはどういうことなのか、子供を殺したということはどういうことなのか、一家を虐殺したとはどういうことなのか、私は二度ならず三度まで手紙をしたためたのだが彼からの返事はなかった。
そんな彼のことがずいぶん気になっていて、幾度か彼の住む島を訪ねようとしたが、飛行機をつかっても最低一週間、もし海が荒れて船が欠航でもしようものなら二週間近くの休暇を覚悟しておかねばならない。そんな長い休暇をとるには一大決心を要することで、なかなかふんぎりがつかずにずるずると時を重ねていたのだ。
ところが今年の賀状の束のなかに、彼の賀状もまじっていた。それを手にしたとき、どんな事態に見舞われたのかわからぬが、彼は再び立ち上がったと思った。彼は挫折することや絶望することを禁じられた男だった。挫折や絶望のなかにではなく、理想のなかに倒れるためにこの世に放たれた男だったのだ。
彼の賀状ほどうれしいものはなかった。というのはその年が終わろうとする十二月の半ばに、四年という長かったのか短かったのかわ