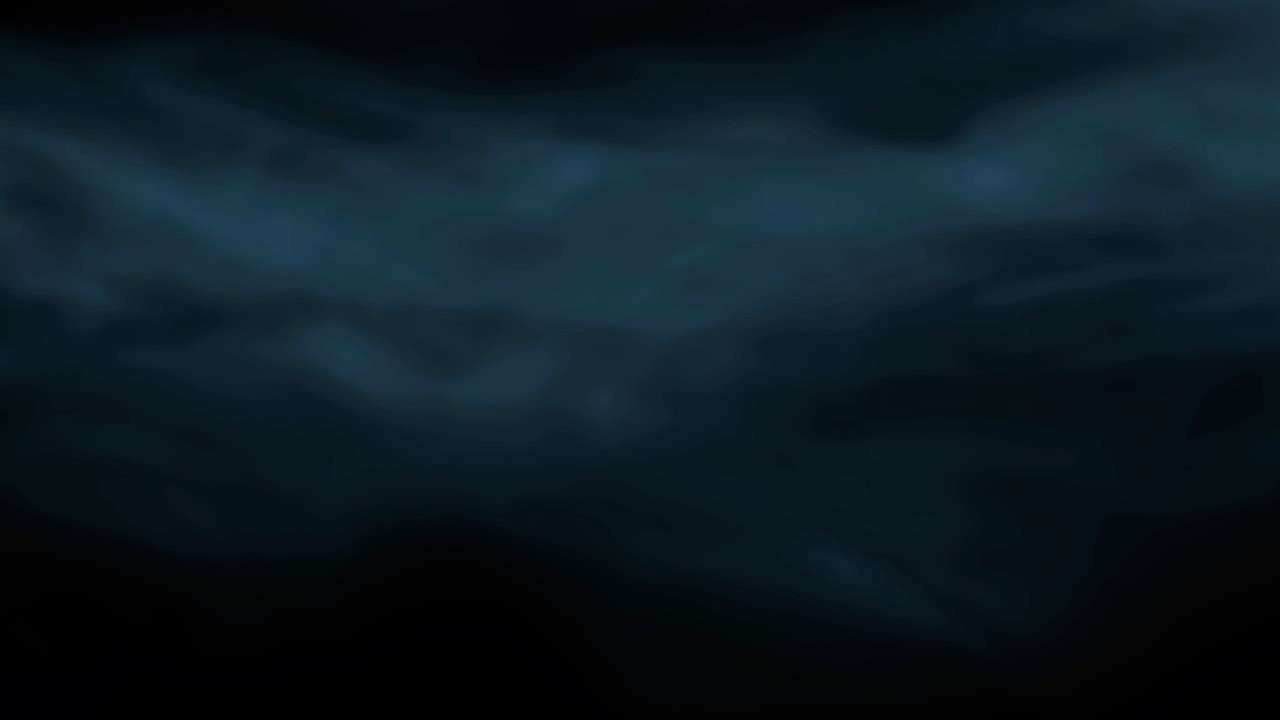なの。あなたは幻に向かって歩いている幻の人なのよ。あなたを追いかける人は、みんな谷底に転落するの。あなたはみんなを谷底に転落させる気なんだわ」
それは愛の言葉なのだろうか。もしそうだとしたら、なんというはげしい言葉なのだろうか。人をひと突きにするほどのはげしさだ。そのはげしい言葉は私の心にも突き刺さってきた。
毎朝、馬や牛の世話をしたあと、わずかな時間を学校に寄って、オルガンを奏でることを日課としていたのだ。それは彼にとって祈りの時間なのだろう。無心にしかしなにか一心にオルガンを弾いている彼の姿をみて、彼が十五のときにイエスに出会ったという話をもう私はげらげらと笑わないだろう。その奇妙な話を次なる事実によって認めなければならないのだ。イエスと出会ったことは幻ではなかったことを証明するために彼は生きているのだという事実によって。
かつて彼は聖書を剣のように構えた戦闘的なキリスト教徒だった。百人もの人間を巻き込んでちょっとした運動を起こしたとき、たしかにもう一つの太陽として輝やこうとしたのである。青春のエネルギーというのはいつも外にむかってほとばしる。だからこそ自我をギラギラとひからせなければならなかったし、聖書だってあんな乱暴な読み方をしなければならなかったのだ。あふれほとばしる青春の情熱がめざすものは愛と理想の王国である。人間は強くなければならない。強ければ強いほど理想の国は近いのである。
しかしいま彼のオルガンは外にではなく、彼の内部にむかって奏でられているように思えた。それはどこにでもころがっている挫折とか絶望がそうさせるのではない。神之島での敗北や、この島でのさまざまな軋轢や障害は彼を強くしたのである。彼のような人間には、失敗とか敗北はそういう現れ方をするように思えた。久しぶりにみる彼は、大学時代のように自信をみなぎらせている男ではなくなっていた。語る言葉はどことなく力がなく、その物腰もまたどことなく弱々しかった。倫子のはげしい愛の告白にうろたえる彼や、青年会での始終開き役にまわっている姿を目のあたりにすると、彼のなかでなにかが変わってしまったように見えたものだ。事実、彼は自信を失っていたし、彼の心は揺れていた。しかし私はその弱々しさのなかに、その揺れる心のなかに土のなかに深くはっていく根をみるのだ。土のなかに深く根がおりていれば、風に吹かれる草のように揺れればいいのである。多くの人間を巻き込むことも、はげしく動きまわることも、自己をいたずらにひからせることも必要ないのだ。
彼の聖書もまたそのオルガンのように彼の内部にむかっているように思えた。結局、人間にはたった一つのことだって実現することができないと彼は言った。だとしたらいったい彼のような人間は、どこにむかって歩いていけばいいのか。どこまでいっても不毛の荒野ではないか。だからこそ神の手が必要なのかもしれなかった。失敗という種を神の手にゆだねるための、幻というかたまりをもった自我を救いだすための神の言葉が。
南海丸は予定通りやってきた。あの若者たちも、小学生や中学生たちも、そして島の人たちも私を見送りにきた。はしけに乗る前に私はもう一度樫山に声をかけた。
「今度は、君がインドにくる番だな」
「そうだな。きっといくよ」
「おれもあの大陸でなにかをはじめていくよ」
「うん、そうだね、まったく」
樫山の目に涙がにじんでいた。そんな彼を見る私もまた涙腺がうるうるとなった。
南海丸は島に向かって幾度か汽笛を鳴らすと、ゆっくりと島を離れはじめた。突堤を子どもたちが船を追いかけるよ