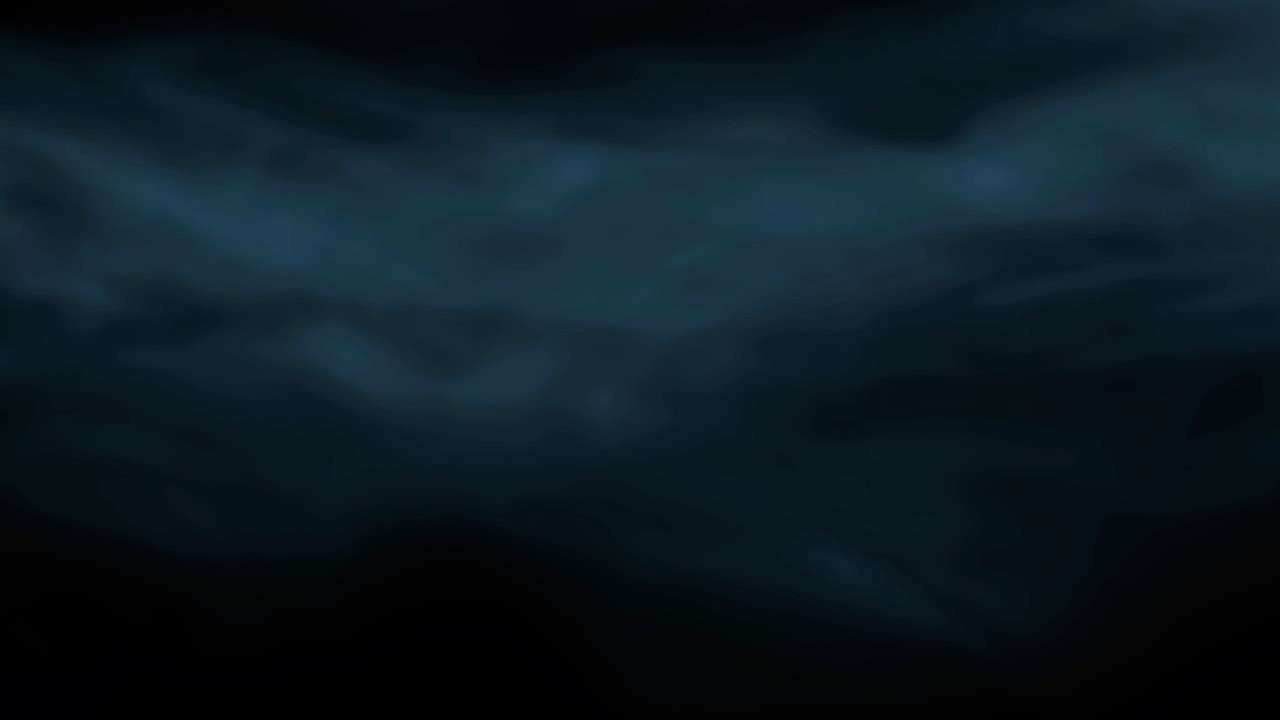本の一・五倍。たとえば、いつも十五軒分自転車にのっけていたのが、十軒分しか積めなくなる。広告の数も増えてホクホクしていたところに、割増の写植代と印刷代の請求が届く。雑誌を厚くするとはこういうことだ。
谷根千の文字は写植。文京区本郷のスマイル企画という写植屋さんで打ってもらっている。「打って」というのは正確ではないな。数年前から電算写植だからワープロのようにキーを「叩いて」文字を入力していく。そして藤間さんが編集機で改行や文字の大きさ、書体を指定してくれる。
さあ、ゲラがでた。ゲラというのは校正刷りのことで、活字を組んで入れる長方形の箱(galley)の名からきたのだった。ちょっと脱線するけど、今から二十年ほど前に精興社印刷の青梅工場を見学した。原稿を見ながらキーを叩き、叩かれて穴のあいた紙を機械に入れると、その先から新しい活字がポンポン作られて並べられていくのを見た。活字作りが機械化されている横では、あの鉛でできた小さな活字の、しかも裏返しになった字をひとつひとつ拾っている文選の人がいた。抬った文字を版面にきっちりと並べる植字の人がいた。私たちは振り仮名をルビと呼ぶけれど、これも活字の大きさで七号(五・五ポ)のことをイギリスではルビーと呼び、それが振り仮名に使う大きさだからなのだとこのとき教わった。本作りには、あの重たい鉛の入った箱を並べてゆく作業が必ずあると思っていた。が、谷根千を作るとき、目の前には写植しかなかったような気がする。
話を戻さなくちゃ。ゲラが出ると原稿と突き合わせて校正をするが、書いた人間と直す人間が同じなので非常に心許無い。そこで小野寺さんに校閲をたのみ、そのほかに編集人三人で読み合わせをする。三人がゲラを手元に置き、回り持ちで読むのを目で追い耳で聞く。「その人はそんな話し方はしない」「ぜんぜん意味わかんないよ」「この話ホント?」なんて、原稿書くときにどうにかして欲しいこともここで直す。「この漢字心配」 「ここで改行しよ」 「アンタの文章〈ネ〉が多いから三つくらい削ろう」「この話〈だそうだ〉くらいにしておいた方がよくない」など。
朝から仕事場に籠もり、留守電にして玄関に配達中の札を下げる。コーヒーをガボガボ飲み、昼ごはんも適当につまみながら、読む。読みながら、聞きとりの語り手のことを話す。取材したときの失敗も話す。腹立ったことも話す。嬉しかったことも話す。Oが突然語り手の声色を使って読みはじめるから、腹をかかえて笑い転げる。一転この密着した時間に、日頃のウップンを晴らすべく、お互いの欠点をあげつらってデスマッチを繰り広げることもある。
夕方、いつも時間切れ。残りの読み合せを超スピードで片づけ、真っ赤になったゲラを持ってスマイル企画に走るのだ。編集機の画面を見ながら赤字を直す藤間さん。直っているかどうか初校と再校ゲラを突き合せ、今度は素読み。「素読トハスットバシテ読ムコトナリ」谷根千。このあたりは急げ急げの大合唱で、できあがったときの赤っ恥がわかっちゃいるけどいつもこうなる。
再校または三校で校了。編集されたフロッピーが動物園のカバほどの大きさの黄色く四角い写植出力の機械にかけられる。
「グィーン、ガシヤ、ガシヤ。グウィーン、ガシヤ。……グィーン、ガシヤ。グィーイーン、ガシャガシヤ」これが黄色い出力カバの鳴き声でけっこう大きい。機械なのに音は不規則で、グィーンというところが「この字はどこかな」、ガシヤは「お、ここだ」に聞こえる。だから難しい字を探すときは「どこかな、どこかな、あれ、ないな、あったあった」