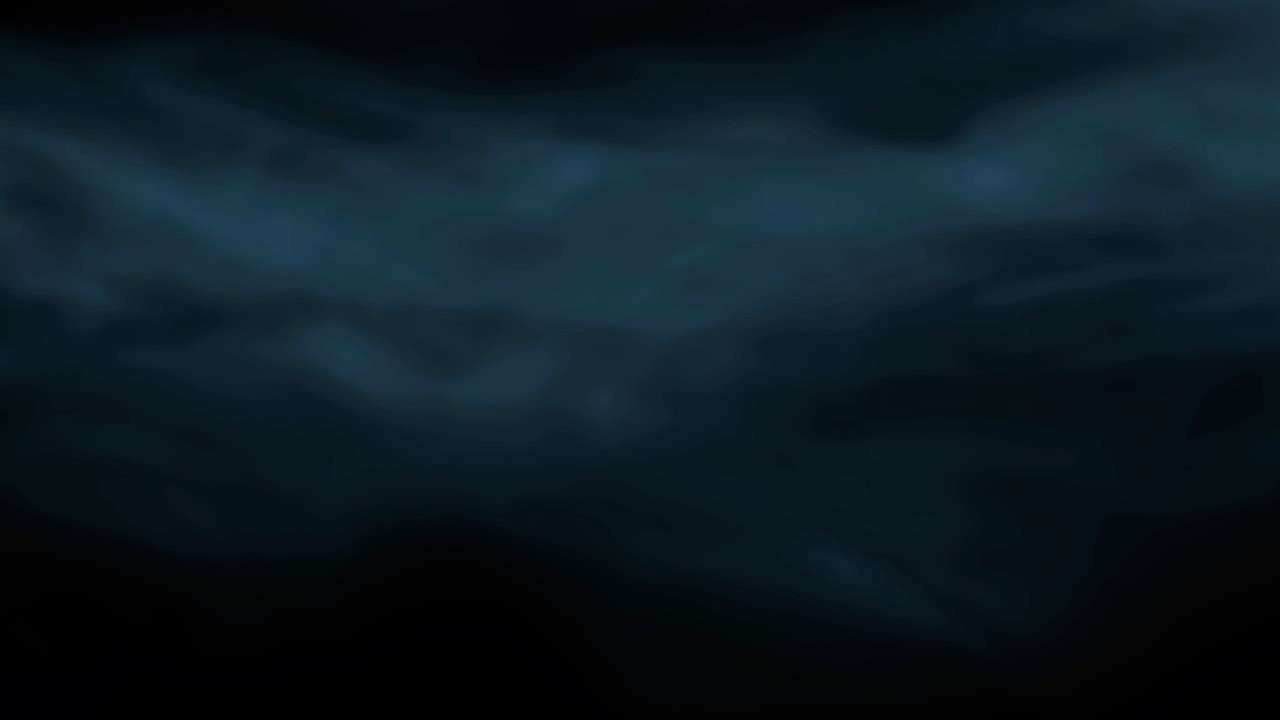腐にシュロップかけたり、ジャムをぬって食べるらしいんだよ、それがセレブなんだって、そうやって食べるのが流行ってんだって、だからさ、あんた、アメリカで流行ってることは、すぐに日本でも流行るからさ、日本のギャルたちもダイエットやるからって、豆腐を買いにくるようになるのよ」
芳江ばあさんは物知りだ。一日中テレビと対面しているためか、セレブだとかギャルだとかいった現代語もちゃんとその会話に登場してくる。毎朝、芳江ばあさんは豆腐屋にやってきて、そんな会話を野口夫婦とすることが日課となっていた。
「あ、雪が降ってきたよ」
「あら、ほんとう。寒いわけね。おばあさん、今日は暖かくして、風邪ひかないようにね」
「はいよ、まあだだよだからね。あんたたちだって、まあだだよなんだからね」
辰雄も七十を三つ越え、則子もまた七十の大台にのってしまった。彼らも十分に歳をとったのだ。彼らもまた決断しなければならない時期にきている。四十年続いた店をたたむという決断を。辰雄はこのところしきりにそのことを考える。いろいろと複雑な問題がこんがらがってからみつき、そのことを考えないわけにはいかないのだ。その問題は辰雄と則子だけで交わされる内輪の話だったが、しかし何十年来のお得意さんたちには二人の胸のうちをお見通しだった。芳江ばあさんは野口豆腐屋の行く末を本気で心配しているのだった。
靴屋
そんな彼にやがて縁談が持ち込まれるのだ。商店街に医院を構える歯医者の夫人からで、もうその縁談相手の女性と会うセッティングまでしていた。そしてこの商店街のボス的存在である野田家具店の野田夫妻から二件も。二人の子供夫婦と一族経営する野田家具店はこの商店街でもっとも大きな店舗で、この店舗を経営する野田夫妻からは、まるで彼らの親族にされたかのように篤史は愛されていた。だから彼らが持ち込む縁談は真剣で、とりわけ二件目などはその話を結実させようと熱く迫ってきた。しかし篤史はその二件ともまったく心を動かさなった。即刻その場で断るのだ。それはまったく取りつく島がないといった反応だった。
その野田夫妻から三件目の縁談が持ち込まれるのだが、それはそれまでの話とちがって、彼の存在を揺さぶるひとつの大きな事件だった。その発端は土曜日の昼下がりだった。一人の女性が彼の店を訪れた。その女はドアを押して店舗に入ってくるなり、
「ああ、ビバルディ!」
工房に優雅に流れている旋律にその女性は感嘆の声を上げた。
「ビバルディがこうして一日流れているんですか」
「ええ、まあ、そうです」
「ああ、なんて幸福なお仕事なんでしょう、ビバルディを聞きながらお仕事ができるなんて、前からこのお店、気になっていたんですけど、とうとうきました、ああ、ビバルディですよね」
そして工房内を見渡して「たくさん道具とか機具があるんですね、ちょっと拝見してもいいですか」といって、手にしてきた紙袋をテーブルに置くと、カウンターの横から工房内に入ってきた。そして一点一点の工具や機具の説明を求めるのだった。
「三台のミシンは、それぞれ違っているんですか」
「ええ、それは作業によってそれぞれ別の用途があるんです」
「これはなんていう機械なんですか」
「フィニッシャーと呼んでいます。皮革を切ったり、削ったり、磨いたり、そぎ落としたりともっとも頻繁に使う機具です」
「これはなんですか、ずいぶん変なものがありますね」
「これはドライヤーです。強力に熱風で皮のたるみとしわを伸ばしたりするんです」
「ああ、たくさんのナイフ、ナイフが壮観ですね」