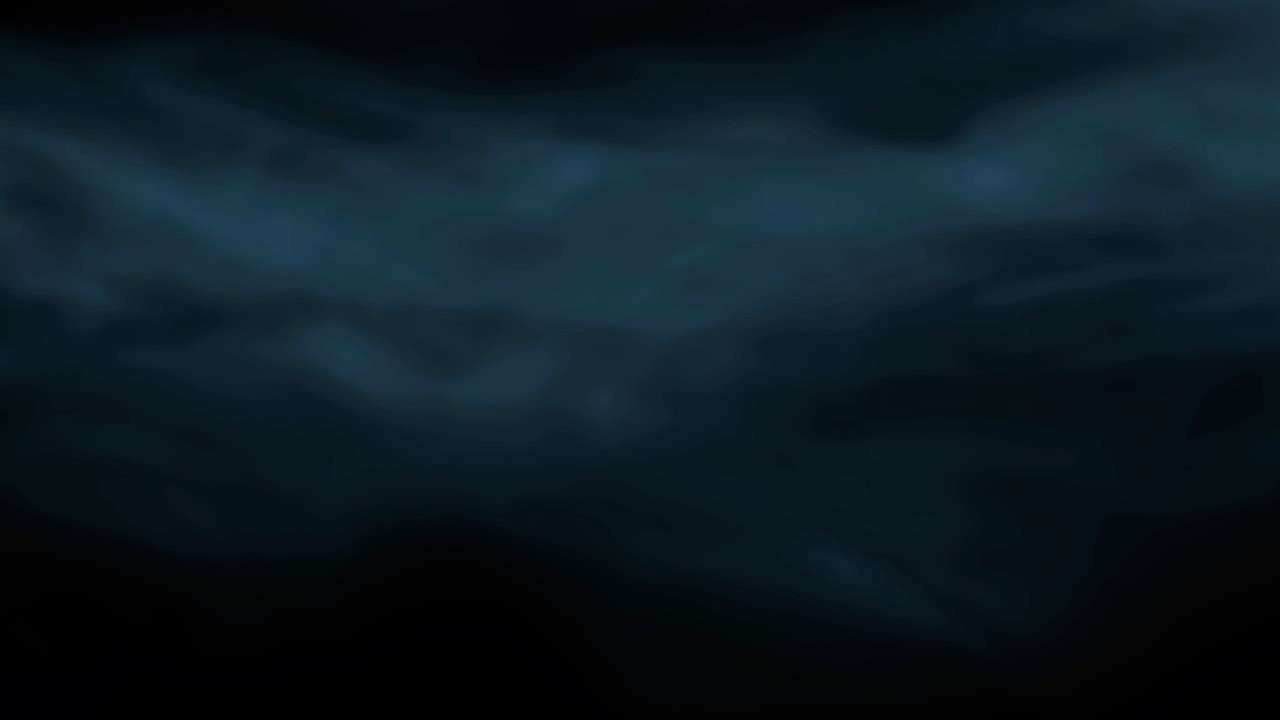ってね」
頭のなかはもう真っ白になり、力という力が抜け落ちて言葉がでません。すると突然、、ははははと野卑な笑い声が、庸子さんの耳に弾き飛んできました。
「驚いたでしょう。嘘ですよ、嘘。だけどさ、あんたのお父さんは、そうしてもいいんじゃないんですか。校長先生やってんでしょう。校長先生ってそうやって責任をとるもんでしょう。子供が一人死んだんですよ。隆君はいってみれば、あんたのお父さんが殺したようなもんじゃないの」
これほど悪質ではありませんでしたが、実はこういういやがらせの電話はもう自宅に毎日のようにかかってくるのでした。朝、昼、夜となく。そればかりではありません。深夜にだれかが石を投げこんで、二階の窓ガラスが粉砕されました。闇からの攻撃は篠田校長だけでなく、家族までに向けられているのです。
庸子さんはこの不快な電話を切ると、青ざめたままクラスに戻ってきました。授業の続きをはじめましたが、クラスがとてもざわついています。もう勉強する雰囲気でありません。でも庸子先生はなにかいやなことをぬぐい去るためにも、むきになって授業を組み立てようとしました。しかし子供たちはなかなかな集中しません。あちこちでざわざわと私語が起こります。とうとう庸子先生は、声をあらげました。「どうしてなの。どうして先生のいっていることをちゃんと聞いてくれないの。最近のあなたたちはおかしいわよ」
最近、本当にクラスの様子がおかしいのです。それまで築かれてきた友情と信頼にあふれたクラスが、なにかどんどん壊れていくように思うのでした。そのことを庸子先生は子供たちに投げかけました。すると一人の子供が、
「先生はいつ校長先生の話をしてくれるんですか。いつかきちんと話してくれるといったでしょう」
その発言は子供たちの胸にたまっていたものに火をつけました。教室はもう騒然となりました。
「うちのお母さんがいってたけど、どうしてあやまらないのかって。校長先生はあやまるべきだって」「うちのお母さんも子供が一生懸命に書いた遺書を、幼稚な遺書だなて馬鹿にする校長は許せないっていってたけど」
「隆君のお母さんがさ、涙をながしてさ、隆の遺書をほめてやって下さい、校長先生、お願いです、隆の遺書をほめてやって下さいっていってんの、全然無視してさ」