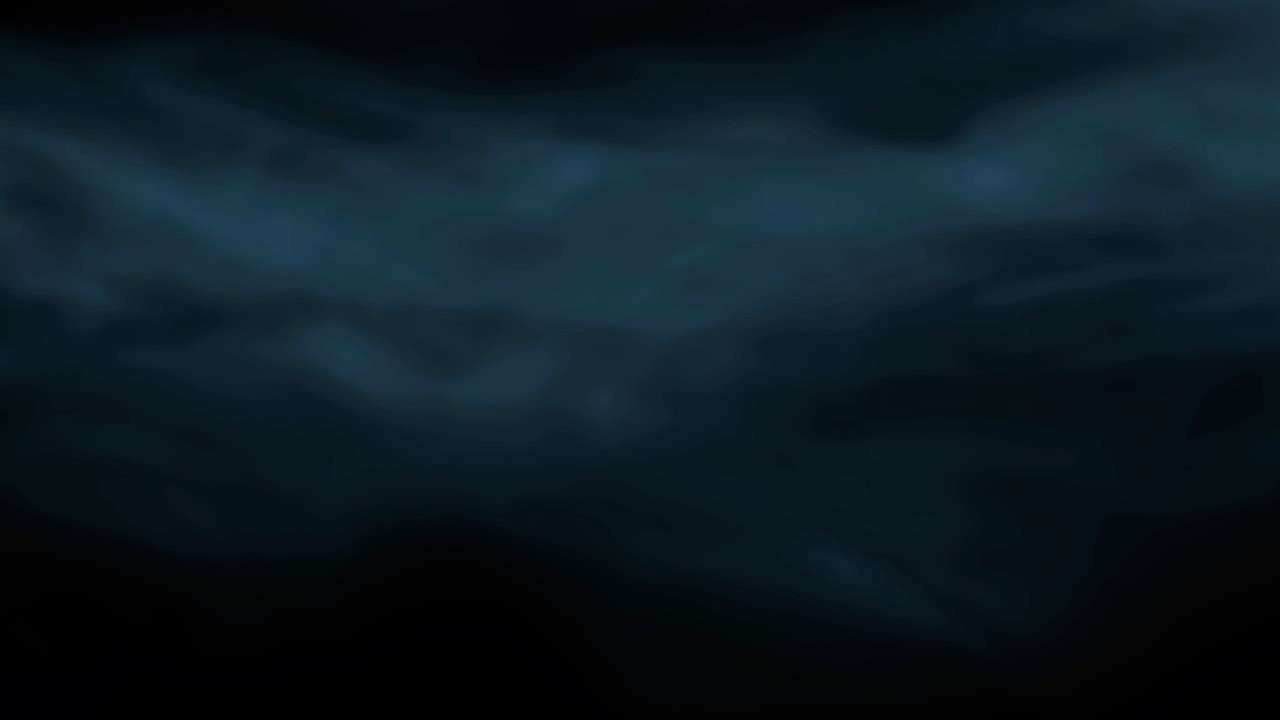に作られたと言っても過言ではありません。
では、何故こんな著名人・有名人・偉人でもない一人の僧侶が亡くなったことを映画化しようと思ったかを簡単に説明させていただき、このプロジェクトに少しでも興味を持っていただいた方へのメッセージとさせていただきたいと思います。
監督『石原ひなた』(21)は典型的なADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害)です。
授業中はじっと座っていることができずに歩き回り、忘れ物・失くし物は日常茶飯事、大好きな日本史(特に戦国期)は教師も知らないマニアックな知識を持ちながら、その反面、興味のない部分は全くと言ってもいいくらい関心を示しませんでした。それは高校生、成人してからも変わりません。
そんな彼の人生で唯一、人に褒められ自信があったものが『写真・映像』でした。
芸術系の大学に入った頃も決して群れず、ひとりで自分の好きなクリエーターの作品を分析するだけの毎日で、自分から“何かを生み出す”生産的・芸術的活動”は何ひとつとして行うことはありませんでした。
私と平井氏の付き合いの性質上(大学教授でもあった平井氏は私のクライアントでもありました)、平井氏の暮らす『宝珠寺』に度々手伝い(主に掃除や行事の準備)として同行させられていた息子は、そこで『平井尊士』に出会います。
息子はこれまで周りにいなかったタイプの大人(とても不真面目。そして真理を説く、“人を良く知る人”)に出会い、次第に傾倒していきました。そして、ふたりの間にある約束が取り交わされたのです。劇中にも重要なシーンとして登場します。
「なんでもええから、写真か映像で賞を獲ってみなさい。それは、あなたが変わったのではなく、次第に周りに変化が起きます。(注:周りの見る目が違ってきます)努力をして結果を出すとはそういうことです。大人と呼ばれる人たちは皆、仕事という形で日常的に行っていることです。」
この約束が監督の心にどう響いたかは分かりませんが、初めて自分から“変わろう”としたまさに矢先の訃報でした。これも劇中では若干の演出が付いているとはいえ、平井氏の訃報が届き、ご自宅に向かう車中で「映画ってどうやって撮るん?」と聞いてきた息子の声は今でも脳裏に鮮明に残っています。
世間ではクラウドファンディングが脚光を浴びはじめた頃。企画が未完成でもとりあえずクラファン。猫も杓子もクラファン。 そんな薄っぺらいチープで浅ましい金集めが横行していた時期。
そんな時期に、機材もない、技術・経験もない、人脈もない状態で監督が始めたのは、自分の足を使っての資金集めでした。
故平井氏のビジネスパートナーでもあった商社取締役・現エグゼクティブプロデデューサーにアポを取り、彼に教わった知識と心構えで全国を飛び回り、自力で数千万円という資金を調達しました。これはADHDの“多動性障害”が良い方向に現れたと思っています。
2018年春から始まったオーディションでは、慣れないながらも大勢の“役者”という初めて会う特殊な業種の方々と接し、何とかクランクインに漕ぎつけることができました。
しかし、主演が本番初日に自主降板という前代未聞・最初で最後の最大のトラブルに見舞われながらも、1年延期した2019年冬に新しいキャスト・脚本で映画は完成しました。
2020年1月18日に行われた完成披露試写会には全国から800人もの方が足を運んでくださいました。その舞台挨拶で、“ハレの日”